プロジェクトについて
設立趣旨
本プロジェクトは、発酵性食物繊維の大切さを広め、健康的な食生活を支援することを目的に設立されました。
<腸からはじまるウェルビーイングな日常>を目指して、さまざまな情報を発信していきます。
協力団体代表者
-
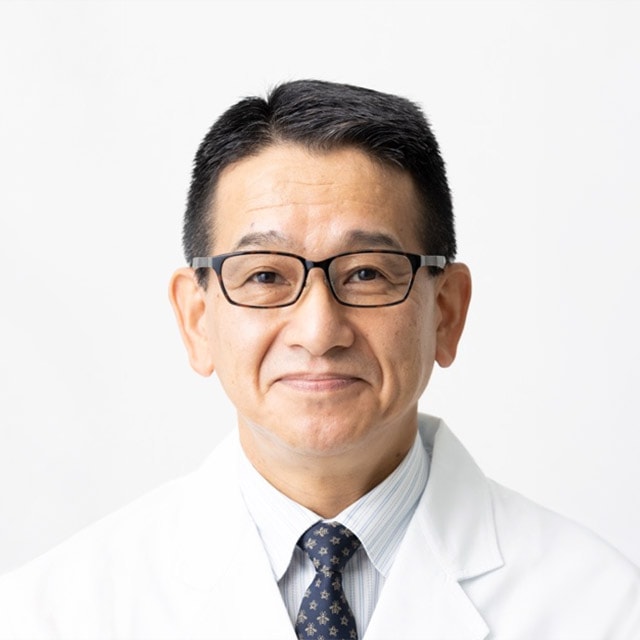
内藤 裕二 先生
- 日本ガットフレイル会議 理事長
- 京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授
PROFILE
京都府立医科大学卒業。米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授、京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学教室准教授などを経て現職。消化器専門医として最新医学に精通し、消化器病学や消化器内視鏡学、生活習慣病、健康長寿や抗加齢医学も専門としている。酪酸菌と健康長寿の関係などの研究をはじめ、長年腸内細菌を研究し続けている。
-
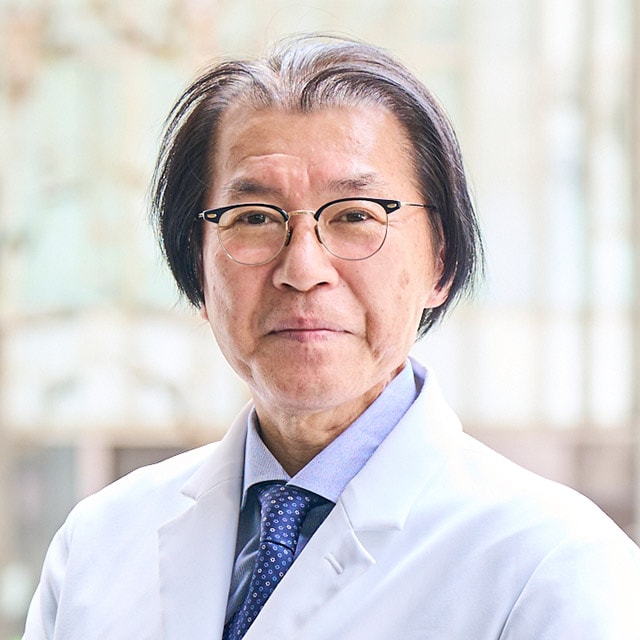
青江 誠一郎 先生
- 日本食物繊維学会 理事長
- 大妻女子大学 家政学部 教授
- 農学博士
PROFILE
千葉大学大学院園芸学研究科農芸化学専攻・修士課程修了。雪印乳業株式会社入社後、千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。大妻女子大学家政学部助教授を経て、2007年より大妻女子大学家政学部教授。2007年日本栄養改善学会・学会賞受賞、2010年日本食物繊維学会・学会賞受賞、2022年日本栄養・食糧学会・学会賞受賞。
今より1日3g以上「発酵性食物繊維」摂取を目指したい
食物繊維の理想的な目標摂取量は1日25g以上ですが、日本人の実際の摂取量はそれよりもかなり低い状態が続いています。その要因の一つは主食である穀類を食べる量が少なくなったことです。日本人の穀類からの食物繊維摂取割合は、1955年には全体の44%でしたが、2018年には20%にすぎません。穀類摂取の減少に伴って、発酵性食物繊維の摂取量も3g/日程度減っています。
発酵性食物繊維には腸内環境の改善など多くの効果があり、もっと摂って欲しいと思います。食物繊維は摂取量が増えるほど健康効果が高まる上に、副作用がなく、食べすぎということはありません。より多くの発酵性食物繊維摂取を目指して、今よりも「プラス3g生活」を始めてみましょう。 -

福田 真嗣 先生
- 短鎖脂肪酸普及協会 代表理事
- メタジェン代表取締役社長CEO
- 農学博士
PROFILE
明治大学大学院農学研究科博士課程を修了後、理化学研究所基礎科学特別研究員、慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授などを経て、同特任教授。神奈川県立産業技術総合研究所グループリーダー、順天堂大学大学院医学研究科特任教授、腸内デザイン学会代表理事、短鎖脂肪酸普及協会代表理事、腸内環境ヘルスケア協会共同代表理事を兼任。2015年、株式会社メタジェンを設立し、代表取締役社長CEOに就任。2024年 Forbes JAPAN 日本の起業家名鑑400、クラリベイト・アナリティクス社 Highly Cited Researcher 2024に選定。著書に「改訂版 もっとよくわかる!腸内細菌叢 “もう一つの臓器”を知り、健康・疾患を制御する!(羊土社)」。
「短鎖脂肪酸」等の有益な腸内代謝物質が健康機能の実行分子として必要不可欠
「短鎖脂肪酸」は脂肪の燃焼促進、脂肪の蓄積抑制、食欲抑制などにより肥満抑制に寄与することが知られています。また、血糖値調節や、免疫機能の増強、持久力の向上など、ヒトの健康維持のみならず機能拡張にも貢献することが近年の研究からわかっています。他にも、妊婦の腸内で作られた短鎖脂肪酸が胎児に影響することで誕生後の子どもが肥満になりにくくなったり、アレルギーを発症しにくい体質になるという報告もあります。
これまで腸内細菌叢は、自律神経や免疫系、心疾患や精神疾患など、全身の様々な健康状態に影響することが報告されていますが、そういった健康機能の実行分子が短鎖脂肪酸などの腸内代謝物質であることが徐々に明らかになってきました。 -
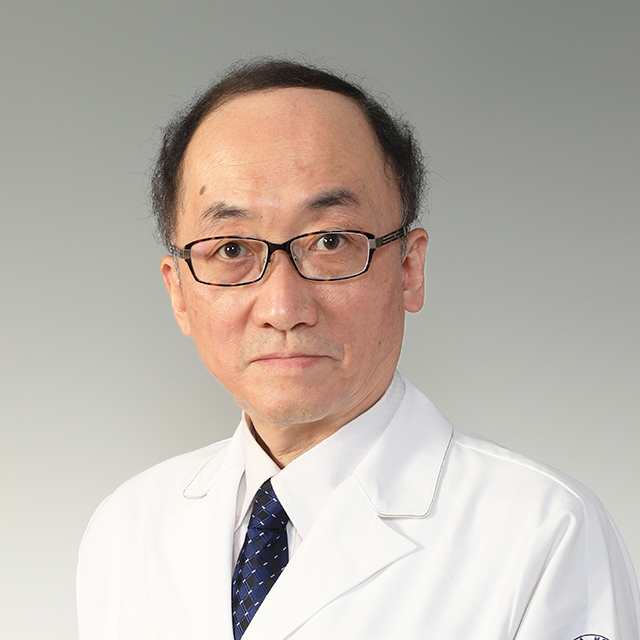
廣岡 芳樹 先生
- 藤田医科大学発 腸活啓発ベンチャー
(株)バイオシスラボ 最高学術顧問 - 藤田医科大学 消化器内科学講座 兼
医科プレプロバイオティクス講座 主任教授
PROFILE
名古屋大学 医学部 医学科卒。医学博士(名古屋大学)。名古屋大学医学部附属病院 光学医療審査部 准教授、藤田医科大学 医学部 医学科 消化器内科学Ⅱ 教授、藤田医科大学 医学部 消化器内科学講座 主任教授。日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会消化器病指導医、日本消化器内視鏡学会指導医、日本消化管学会胃腸科指導医、日本膵臓学会認定指導医、日本胆道学会認定指導医、日本超音波医学会超音波指導医(消化器)、日本医師会認定産業医など多数の資格を持つ。
藤田医科大学発の腸活啓発ベンチャー(株)バイオシスラボで臨床医・研究者としての知見を健康づくりに還元
消化器内科の臨床を基盤に腸内細菌叢と疾患の関係を精密に検証し、その成果を患者を助ける実際の治療へとつなげるため、プレバイオティクス研究に注力しています。細菌叢を調べるだけでは不十分であり、臨床の現場で真に役立つプレバイオティクスこそが必要であるとの信念のもと、病気の改善や再発予防、さらには疾患予防の実現を目指しています。
さらに、藤田医科大学発の腸活啓発ベンチャー株式会社バイオシスラボの最高学術顧問として、日夜プレバイオティクスの啓発活動も推進。研究と社会実装の両面を担い、臨床医・研究者としての知見を未来の健康づくりに還元しています。 - 藤田医科大学発 腸活啓発ベンチャー
発酵性食物繊維普及プロジェクト事務局長コメント
-

西沢 邦浩 事務局長
- 一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクト 事務局長
PROFILE
早稲田大学卒業。小学館を経て、1991年日経BP入社。2005年より『日経ヘルス』編集長。2008年『日経ヘルス プルミエ』を創刊し、編集長。2012年から15年まで、日経BPと三菱商事の合弁コンサルティング会社テクノアソシエーツのヴァイスプレジデント。2016年から日経BP総研マーケティング戦略研究所 主席研究員。2018年、株式会社サルタ・プレスを設立し代表取締役、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボ客員研究員に。ほかに、おいしい健康ラボ所長、同志社大学生命医科学部委嘱講師、一般社団法人日本ガットフレイル会議エグゼクティブ・アドバイザーなどを務める。
発酵性食物繊維を正しく理解し、無理なく十分な量をとってもらうために
私たちは、自分の体を構成する約37兆とされる細胞と同等かそれ以上の数の腸内細菌と共棲し、健康を維持しています。そのため、食事には、これらの細菌たちが元気に活動するために必要なエサが十分に含まれていなければなりません。そのエサこそが、消化吸収されずに腸の細菌たちに届く発酵性食物繊維です。
しかし、発酵性食物繊維のうちで大きな割合を占める水溶性食物繊維を見ても、かつての半分程度の摂取量(約3g減)まで低下しています。
そのため、まだまだ混同がある「発酵食品との違い」、「サラダで生野菜をとってもあまり発酵性食物繊維はとれないこと」などをわかりやすく説き、日々の食生活で無理なく必要な発酵性食物繊維がとれるよう、情報発信を始めとする普及活動を進めてまいります。



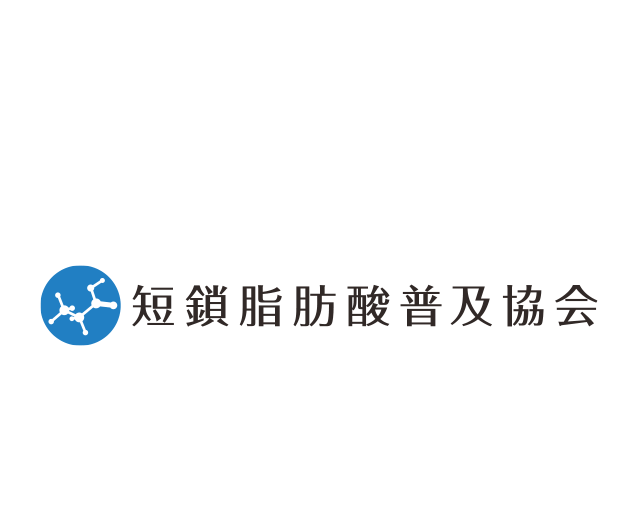
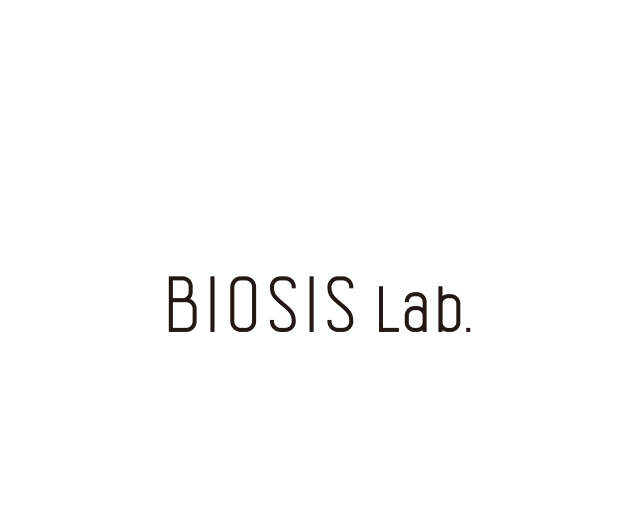






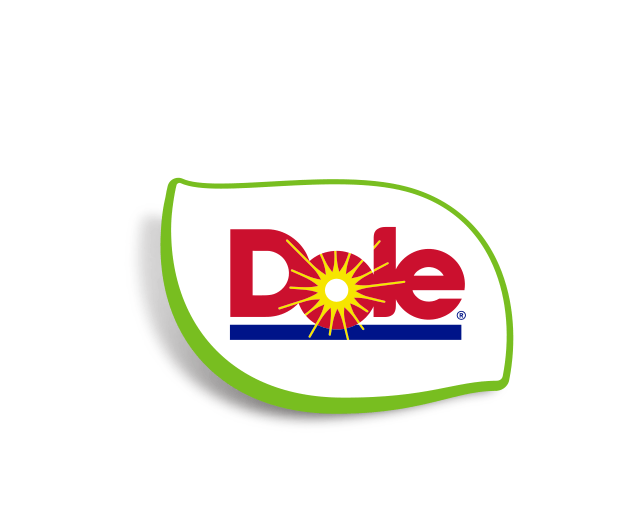









「発酵性食物繊維」で理想の腸内細菌に近づける
腸内細菌が老化とも密接に関係していることがわかってきました。若いマウスの腸内細菌の移植で老齢マウスが若返ったという報告もあります。こういった腸内細菌を介した長寿の秘密に迫ろうと、日本で有数の長寿地域・京丹後地域でコホート研究をしています。研究は途上ですが、そこでわかってきたのは京丹後の健康な高齢者には「短鎖脂肪酸」を作る腸内細菌が多いこと、「発酵性食物繊維」を多く含む食材を食べる頻度が高いことです。この結果を踏まえて、研究チームでは長寿につながる日本人の食事パターンを見つけ出そうとしています。発酵性食物繊維が豊富な和食で健康長寿を目指しましょう。